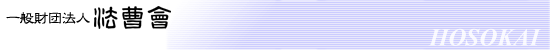 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2010年6月発行 |
| 知的財産訴訟の実務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産裁判実務研究会編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍コード | 300020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 判型 | A5判上製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頁数 | 368頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産権をめぐる最近の状況は,めまぐるしく変化しつつある。まず,2002年3月には知的財産戦略会議が設置され,同年11月には知的財産基本法が成立し,2003年3月には内閣総理大臣を本部長とする「知的財産戦略本部」が内閣に設置され,「知財立国」の実現に向けて,「知的財産推進計画」が毎年作成されている。 知的財産戦略本部が設置されてから,知的財産を戦略的に保護・活用し,我が国産業の国際競争力を強化することが国家目標とされ,さまざまな制度改革が推進されてきた。このような状況の中で,知的財産権が侵害されたときに,その損害をすみやかに回復し,差止め等の措置を採るために,裁判所において適正迅速な裁判がなされることが各界から期待されているのは当然のことであろう。 知的財産権関係訴訟事件の充実・迅速化は,2001年6月の司法制度改革審議会の意見書においても最重要課題の一つとして位置付けられていた。そして,2003年には民訴法(知財訴訟関係)が改正され,特許権,実用新案権に関する訴訟の東京・大阪の裁判所への専属管轄化,著作権・商標権に関する訴訟の東京・大阪の裁判所の競合管轄化,知財訴訟への5人合議制の導入,専門委員制度の導入がなされた。 裁判所においても,この間,知財訴訟の果たす役割の重要性と各界からの期待を真摯に受け止め,知財訴訟部門の裁判官,調査官の大幅な増員を行い,若手裁判官の海外及び国内の研修を充実させ,また,知財関係の国際会議に経験豊富な裁判官を積極的に派遣するなどし,日本の知財訴訟を海外にもアピールしてきた。また,東京地裁の知財部では,2000年10月に「知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言」をまとめて公表し,2003年5月にはこれまでの審理運営におけるさまざまな試みを集大成した「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」(司法研修所編・法曹会発行)を発行している。 この結果,知財訴訟の既済事件の平均審理期間は,ここ10年でほぼ半減し,その迅速性においても予見可能性においても知財の専門家から高い評価を受けるに至っている。 また,2005年4月には,知財高裁が設立され,審決取消訴訟及び侵害訴訟控訴審の一層の審理の充実と迅速化が図られ,さらにはこれまでに大合議による判決もなされるなどして,社会的な注目度及びその影響力が一段と高まってきているといえよう。なお,2005年4月には,特許法の改正により秘密保持命令の制度や無効の抗弁の制度が導入されるなどしており,これらの改正が知財訴訟の審理に実質的な影響力を与えつつある。 本企画は,このような状況の中で,東京・大阪地裁知的財産部の裁判官有志及び知財高裁の裁判官有志が,特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権の各侵害訴訟,不正競争防止法に基づく訴訟,職務発明相当対価請求訴訟及び審決取消訴訟の実務について,実体法及び訴訟手続の観点から実務上重要と思われる点をなるべくわかりやすく解説し,知財訴訟に興味のある法律家に,広く知財訴訟の実務を理解してもらうことをその目的とするものである。したがって,見解が分かれる法律上の争点については,できるだけ客観的に判例学説の考え方を紹介することを原則とするが,その中で表明されている見解があるとすれば,それは文責者の意見であり,東京地裁・大阪地裁あるいは知財高裁としての公式見解でないことはいうまでもない。本企画が,知的財産法に興味のある一般の法律家が知的財産関係訴訟についての理解を深める一助となれば幸いである。 (本書 はじめにより)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||