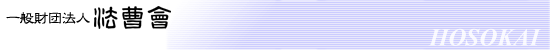 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2016年12月発行 |
| 簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究 | |||||||
| 司法研修所編(司法研究報告書第67輯第1号) | ISBN 978-4-908108-67-9 | ||||||
| 書籍コード 28-19 | A4判 188頁 | 税込定価 3,259円(本体 2,963) | |||||
|
本研究は,簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件(ただし,物損事故事件に限る。)の審理・判決の在り方を研究するものである。 物損事故事件は,実況見分調書が作成されないなど客観的な証拠が少ないことから,事実認定に悩むことが多く,裁判官にとって難しい事件の一つといえる。しかし,低額の物損事故事件は国民に身近な紛争の一つといえることから,国民に身近な紛争を簡易迅速に解決する役割を担う簡易裁判所において解決するのが望ましい。ところが,簡易裁判所の物損事故事件は弁護士保険特約の普及に比例して年々増加しており,これに伴って審理期間が長期化し,判決書作成にかかる裁判官の負担も増大している。また,これまで本人訴訟を中心に審理運営を行ってきた簡易裁判所の裁判官が弁護士に適切に対応できているかという問題もある。簡易裁判所の物損事故事件の審理・判決は現在このような状況にあり,このままでは簡易迅速な審理・判決の実現という簡易裁判所の役割を果たせないのではないかとの懸念がある。そこで,弁護士関与訴訟にも対応できる物損事故事件の在るべき審理・判決モデルを作成し,これを簡易裁判所の裁判官に実践してもらうことによって簡易迅速な審理・判決を実現しようとするのが本研究の目的である。 本研究に当たっては,研究員・協力研究員において簡易裁判所の判決書を100通以上分析し,汎用性のある判決モデル案を作成した。その上で,その判決モデル案を東京,大阪,名古屋及び横浜の各地方裁判所の交通部裁判官並びに簡易裁判所における物損事故事件について豊富な経験を有する東京の弁護士4名(伊藤まゆ弁護士,垣内惠子弁護士,円谷順弁護士,飯島雅人弁護士)の方々に見ていただき,控訴審及び当事者の立場から貴重なご意見を頂いた。また,東京の弁護士4名の方々には実際に本報告書を読んでいただき,本報告書に対しても数々の貴重なご意見を頂いた。本研究にご協力いただいた各地裁の交通部裁判官及び弁護士の方々に対し,心からお礼を申しあげたい。さらに,東京簡易裁判所の裁判官及び書記官の方々からも本報告書で示した審理・判決モデルに対して有益なご意見を頂いた。併せてお礼を申しあげたい。 このように本報告書で示した審理・判決モデルは,控訴審の立場,当事者の立場,簡易裁判所の立場から頂いたご意見を踏まえて作成したものであるが,最終的な責任は本報告書を作成した研究員・協力研究員にあることはいうまでもない。また,本報告書に記載した争点整理及び事実認定に関する基本的な事項並びに民事訴訟法280条を活用した判決書の記載事項は,物損事故事件以外の民事訴訟事件にも応用できると考えている。本報告書が,簡易裁判所の物損事故事件の審理・判決にとどまらず,それ以外の事件の審理・判決にも参考になれば望外の喜びである。 最後に,司法研修所,最高裁判所事務総局民事局,各研究員・協力研究員所属の裁判所には,本研究について多大なご配慮を頂いた。ここに改めて謝意を表したい。 (「はしがき」より)
|
|||||||
目 次
|
|||||||